特集
特集
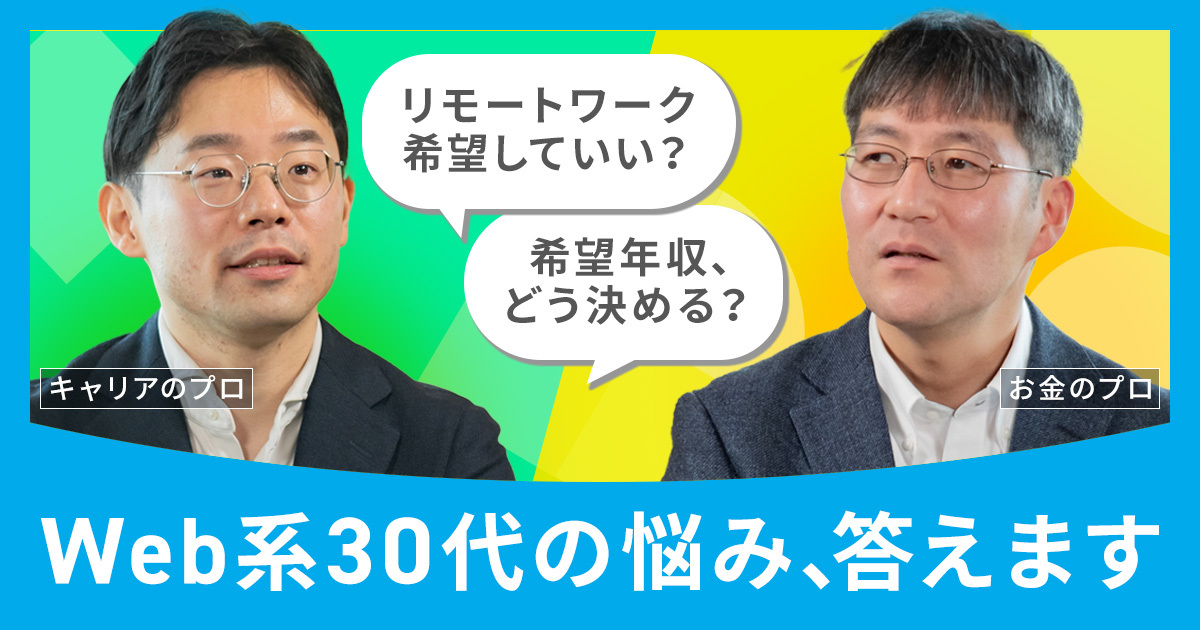
身についた専門性があるし、人生計画もあるし、若い頃のように大胆なキャリア選択が難しくなってきた……。何を意識して転職を考えたらいい?
30~40代のミドル世代のキャリアとお金の悩みに、それぞれの専門家が答えます。
第1回は、IT特化型転職エージェント「レバテックキャリア」の芦野成則さんと、さまざまな年齢・職業の方のお金についての相談に応じてきたファイナンシャルプランナーの横田健一さんに、30代のWebエンジニアの悩みをぶつけてみました。

レバテック芦野成則(以下、芦野):前提として現在のエンジニアの採用市場は売り手市場のため、年収を上げて転職するケースが多いですね。弊社でご支援した方々も約8割が年収アップを実現しています。そのため、現在の年収より高い金額を希望年収とすることは問題ありません。
一方で、高すぎる希望年収を伝えてしまうと、企業からそれに見合うスキルが本当にあるのか? とややネガティブな目で見られたり、仮に転職できても入社後に金額に見合った活躍ができなかったりというリスクがあります。基本的には「現年収より気持ち高め」程度の金額を希望年収とするのがおすすめです。
客観的に自分の価値を把握するのは難しいですし、転職エージェントを利用するメリットの一つは、適正な希望年収を相談しながら一緒に決められること。意外なスキルや経験が転職市場では評価されることもあります。過去の事例も踏まえてアドバイスをもらえるはずなので、「どれくらいが適正かわからないのですが」と素直に伝えていただいて大丈夫ですよ。

芦野 成則
レバテック ITリクルーティング事業部
一橋大学を卒業後、官公庁に5年半勤務し、2019年にレバレジーズに中途入社。レバテックのキャリアアドバイザーとして、年間約300人以上のエンジニア・ITコンサルタント向けのキャリア支援に従事。
現在は、主にミドルからハイレイヤー層を中心とした採用支援を手がけ、人事視点に基づく現状分析や、IT人材の転職市場動向を踏まえた多角的な支援を実施している。
——「高すぎると逆に期待に応えられない可能性がある」というのは長期的に働くうえでは大切ですね。マネープランを設計するうえではどのようなポイントを意識して「必要な年収」を考えればよいのでしょうか。
ファイナンシャルプランナー横田健一(以下、横田):額面の800万円、1000万円といった数字“以外”の部分が意外に大切なので、ぜひ転職者の方にも意識してほしいですね。
例えば、退職給付制度。いわゆる退職金に加え、最近だと企業型確定拠出年金制度がある企業も増えてきました。人生100年時代、公的年金の上乗せとして老後にどれぐらいお金をもらえるかという観点で、企業がもつ制度を見ることは大切だと思います。上場企業でありながら退職給付が一切ないケースも結構多いんですよ。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、30人以上を雇用する民間企業のうち、退職給付制度がある企業は全体の74.9%となっています。その内訳は、退職一時金制度のみが69.0%、退職年金制度のみが9.6%で、両制度の併用が21.4%。制度自体がない企業は、24.8%という結果になっています。
芦野:エージェントの立場でも、退職給付の有無についてアドバイスすることはありますね。他に単純な年収ではない観点ですと、もともとの勤務時間が短めな会社であれば、時間あたりの賃金は高くなるので、そのあたりに触れることもあります。
横田:1日1時間違えば、1年間で相当な時間になりますもんね。福利厚生も軽視できません。最近ではベネフィット・ステーションなどの福利厚生サービスを導入している企業も多いのですが、旅行先の宿泊で1泊数千円が割引になることも。福利厚生だけで選ぶ必要はありませんが、転職先候補はもちろん、改めて今の会社の状況を確認する価値はあると思います。
芦野:「いろいろ総合して考えると、思ったより今の会社、条件いいな」なんてこともありますね。

芦野:この相談は実際に大変多いですね。結論を先にいうと「あり」だとは思います。弊社の調査でも、6割程度のエンジニアの方がマネージャーへのステップアップを希望していないという結果が出ています。
ただ一方で、マネージャー経験がある人のほうが企業からの需要が旺盛かつ採用市場への供給も少ないため、市場価値は高いのも事実です。コーディングができる“だけ”では、同世代のマネージャーと同じ水準の年収をもらうことはなかなか難しい。組織で成果を出すマネージャーと同じぐらいの事業インパクトを、個人のプレイヤーでも起こせるかが大事になるので求められるものは当然高くなります。そのあたりを転職希望者と深めていくことが多いですね。
そもそも「マネジメントに興味がない」と一言で言っても、人事評価をしたくないのか、手を動かす時間が減るのが嫌なのか、組織目標を背負うのがプレッシャーなのか……理由はいろいろです。そこを丁寧にヒアリングしていくと「こういう形ならいいかもしれない」「むしろチャレンジしてみたい」と心変わりするケースも少なくありません。
——プロフェッショナルなプレイヤーとして極めていくのであれば、独立して開業するようなケースもありますよね。会社員とはやはりマネープランの考え方が変わってきますか?
横田:過去の私の相談者の中には、デザインの仕事で独立して複数の企業から業務委託を受け、売上が数千万円に達したという方もいらっしゃいました。それは成功例だと思いますが、独立するとそのようなアップサイドがある一方で、社会保険をはじめとする公的な保障が限定的になるという現実もあります。個人事業主などでは、そういった点が手薄になりがちなので、見た目の年収に限らず自らの備えも考慮する必要がありますね。
特にエンジニアの話でいえば、例えば、海外企業に発注すれば人件費が安く済むとオフショアで開発を進める会社も増えています。生成AIの進化によって、AIがコードを書いてくれる領域もさらに広がっていくかもしれません。そういった時代の流れのなかで、自分の価値をどう磨いていくかを考えるのは、とても大事なポイントかもしれません。

横田 健一
ファイナンシャルプランナー
株式会社ウェルスペント 代表取締役
野村證券株式会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年に独立。FPとして家計相談やライフプランシミュレーションの実績多数。
「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。2023年6月、初の著書『新しいNISA かんたん最強のお金づくり』(河出書房新社)を発売。「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」監修。
芦野:まったくおっしゃる通りです。日本企業は国内でエンジニアを確保するのに限界を感じており、コードを書く部分は海外に任せて、日本にいるエンジニアにはビジネスに近い領域の仕事やマネジメントを任せる動きは顕著です。だからこそ、プレイヤーとして生きる場合、一点突破できるスキルや、覚悟をもっていないと先々しんどくなるかもしれません。
——マネジメントを「ビジネスを生み出すポジション」と考えると、興味をもつ方が増えそうですね。
芦野:技術とビジネスが不可分になりつつある今、エンジニア的な視点のニーズは増えています。例えば、企業の求人情報の中で最近増えている職種名が、「プロダクトエンジニア」。技術を理解しつつ、言われたものをつくるのではなく、プロダクトをどうよくしていくか、事業をどう成長させるかを考えていくポジションです。2024年によく目にした職種名ですが、2025年以降もどんどん増えていくのではないかと予想しています。

芦野:こうした相談を受けた場合、なぜベンチャーに移りたいのか、まずは理由を詳しく聞きます。実は今いる会社や部署が嫌なだけで、ほかのSIerに移れば解決するようなケースもあるので。
また、ベンチャーといっても、社員が数名しかいないスタートアップなのか、すでに上場している企業なのかでまったく違いますよね。名の知れたメガベンチャーなどは、「大企業」としての特徴を備えている側面もあると考えられます。転職先を決めるうえでどのようなこだわりがあるのか、深掘りしてお伺いしますね。
「大手企業からベンチャーに転職すると、年収が下がるんじゃないか」と言われることがありますが、実は日本経済新聞社が実施した調査(NEXTユニコーン調査、2023年)では「スタートアップの平均年収が700万円を超え、上場企業を上回る水準になった」という結果が出ていたりするんです。なので、年収水準について大きく心配する必要はないと思っています。
それよりは、教育体制が未整備だったり、事業がスピーディーに変化していったりという、ベンチャーならではの環境への耐性があるかどうかが大事ではないでしょうか。

横田:転職に際して年収のアップダウンを考えるときもそうですが、生活費にどれぐらいの金額を使っているかをざっくり把握しておくことはキャリア選択のうえで大切だと思っています。
例えば年収が700万円だとして、社会保険料や税金がおおよそ150万円だとすると、手取り収入は500万円台半ばになります。そこから生活費としてどれぐらい使えるか。将来に向けた資産形成、子どもの教育費、住宅ローンなどもありますよね。
その場合、1円単位で家計簿をつける必要はありません。年間300万円使っているのか、500万円使っているのか、程度のだいたいの金額を把握しておけば十分でしょう。会社員の方であれば源泉徴収票に記載の金額から手取り収入はわかります。クレジットカードなどの各種引き落としが給与口座と同じであれば、1月1日から12月31日までの給与収入の手取り金額、預金残高の増減を比べれば、おおよその支出を把握できるのでぜひ計算してみてください。

横田:人それぞれにどういったライフイベントを想定するかは異なると思いますが、結婚したい、家を買いたいなど、「何年後にはこんなことをしたい」といったライフプランをざっくりとつくっておくといいでしょう。
そのうえで、それぞれのイベントにどれぐらいの費用がかかるかを把握する。イベントごとの平均の費用はすでにデータで出ていますので、ライフプランをもとに「何年後にこれだけの金額が必要になる」というのが見えてきます。そうすると、それに備えて毎月いくら貯金しようといった具体的な行動に落とし込むことができ、漠然とした不安を払拭できると思います。そのためにも、先にお伝えした収支の把握はやはり大切ですね。
加えて、公的な経済支援の制度についても事前に簡単に調べておくことをおすすめします。例えば出産や育児にあたっては、出産手当金や育児休業給付金、出産育児一時金が給付される制度があります。住んでいる自治体によってもさまざまな制度が整っているので、制度の活用も合わせて、ライフプランについて考えてみましょう。
大きな決断だからこそ不安になる気持ちはもちろんわかるのですが、漠然と悩む前に、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。

芦野:海外のテック企業や大手IT企業でも出社回帰の傾向が見られますし、この先いずれの企業でもフルリモートが続くことは考えにくいかもしれません。そのため、リモート環境での就業を前提に地方に移住したりするのは、危険かなと思いますね。
ただ、弊社の調査では、完全にリモートワークを廃止する会社はまだ若干数です。リモートと出社を合わせたハイブリッドな勤務体系の会社にはそこまで変動はなさそうです。100%フルリモートを希望するのでなければ、自分の生活に合った仕事の仕方ができる会社を見つけるのに苦労はしないと思います。
とはいえ、そもそもスキルがなければ希望する就業形態の企業へ転職することは難しいでしょう。自分のもつスキルをいかに高めるか、常に考える必要がありますね。

——リモートワークするかどうかを考えるにあたって、FPの観点から「こういった点も考慮するといいかも」というポイントがあれば教えてください。
横田:例えば、東京の都心部で公共交通機関を使って生活するのか、地方の車移動がメインのエリアで生活するのかでは、後者のほうが家賃水準は安くなってもガソリン代はかかるなど、それぞれの支出の内訳も変わります。リモートワークも絡めて住む場所を決める場合は、家計全体の収支のバランスがどう変わるか、考慮することが大事ですね。
以前、「緑のある場所で子育てをしたい」と、それまで住んでいた東京23区から緑に囲まれた地域に家を買って移り住んだ相談者の方がいました。一方で、「子どもには中学受験させたい」と考えて、学習塾に通わせることを念頭に都心に住み続けるご家族もいらっしゃいます。パートナーの考え方もあると思うので、そこを二人ですり合わせながら、働き方や住む場所などを探っていくといいのではないでしょうか。
——お子さんを含め、ご家族とどのような生活を送っていきたいか、長期的な観点で設計できるとよさそうですね。
横田:教育プランもふまえ、リモートワークを活用して子育てしていくのか、出社を前提に都心で生活するのかなど、お子さんが独り立ちするまでの長いスパンを見据えて考えることが大事かなと思います。
あとはどこか違うエリアへ移り住む場合、いきなり住宅を購入せず、まずは賃貸で引っ越すことをおすすめします。その後の選択肢の自由度は、賃貸のほうが明らかに高いですからね。
——キャリアプランとマネープランを一緒に考えることで広がりがあり、とても勉強になりました。読者のみなさんそれぞれの悩みがあると思いますし、さまざまなケースを知っているプロに早めに相談すると発見がありそうですね。
芦野:キャリアとお金の話は本来はとても近いものですもんね。人生100年時代と言われますが、長い人生を見据えると、貯蓄があることや資産形成をしていることで、キャリアや生き方の選択肢を増やせるのだなと改めて感じました。
私自身も、求職者のみなさんの悩みを聞いていても、同じように感じていたのですが、実際にFPの方の視点でお話を聞けて、非常に参考になりました。
横田:以前は“就活”ではなく“就社”だと言われているなど、働く方々は会社への帰属意識が強かったと思うのですが、今日のお話を伺って自分のバリューをどう高めていくか、スキルをどう高めるかを意識しながら転職について考えている方がとても多いんだなと思いました。
お金の面でも最近の若い方々は、当たり前のようにNISAやiDeCoをやっていますし、聞いた話では新卒の採用試験を受けている学生さんが「御社は確定拠出年金制度を導入されていますか」という質問をしてくることもあるそうです。我々の世代とは意識が変わってきていることを感じますね。
(構成:加藤智朗、編集:山崎春奈、撮影:工藤朋子)