特集
特集
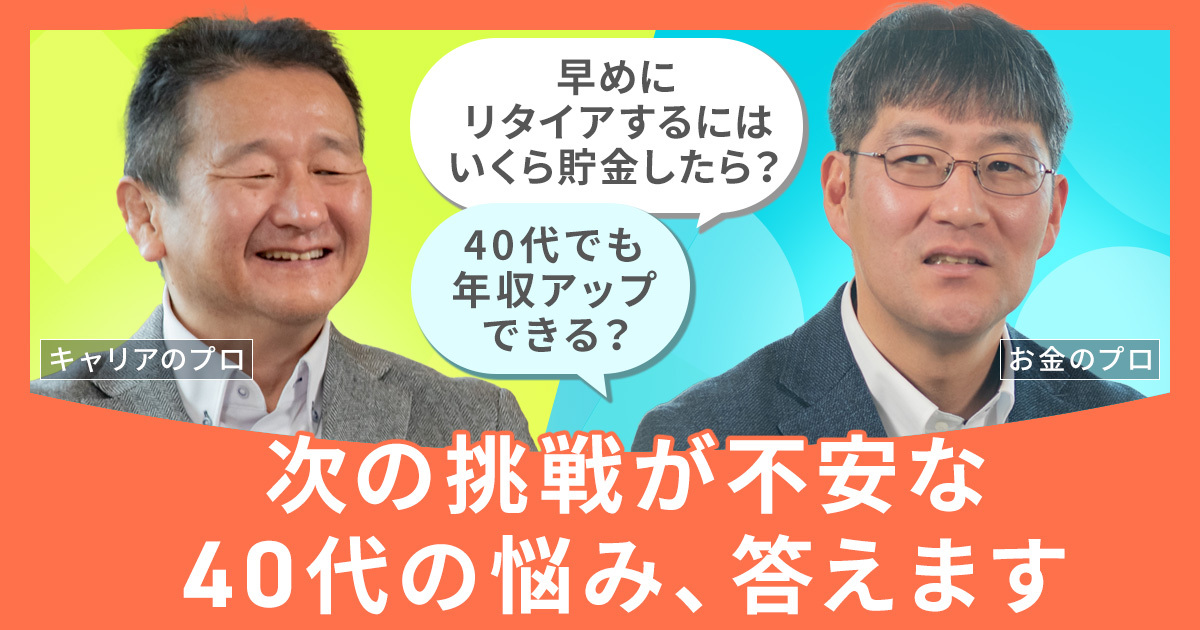
身についた専門性があるし、人生計画もあるし、若い頃のように大胆なキャリア選択が難しくなってきた……。何を意識して転職を考えたらいい?ミドル世代のキャリアとお金の悩みに、それぞれの専門家が答えます。
第2回は、転職支援だけでなく、事業承継・M&A仲介の事業も手掛けるヒルストン代表取締役・石坂裕さんと、さまざまな年齢・職業の方のお金についての相談に応じてきたファイナンシャルプランナーの横田健一さんが聞き手です。40~50代のベテラン層の悩みをぶつけました。

ヒルストン 石坂裕(以下、石坂):20代から30代前半までの転職は、ポテンシャル採用の面もあり、新しい会社に入ってから能力を身につけることを期待されます。それに比べると、40代以上の転職では、企業からそれまでに培ってきた経験や能力をシビアに見られるのが大きな違いです。転職を考える際には、まず自分が新しい会社に対してどんな部分で貢献できるか、これまでの経験をしっかり棚卸しして見極める必要があると思います。
「35歳を超えると求人数が少なくなる」という話もありますが、昨今のデータを見ると40代以上を対象にした求人も明確に増えてきているのはプラスの事実です。とはいえ、潤沢に選択肢があるかと言えばやはり35歳以下と比べると少ないのは間違いありませんし、何より見る目が厳しくなります。
——となると、年収が下がるケースも少なくないのでしょうか?
石坂:もちろん年収アップがベターですし、それを目指す方が多いのですが、「最低でもこの水準はキープしたい」と、現実的な年収の下限を設定して転職されるケースが多い印象ですね。
各々で優先順位は異なると思いますが、子どもの教育費や家のローンの支払いなどを踏まえ、「これ以上は下げられない」という年収のラインを軸に転職先を考えていくイメージでしょうか。

石坂 裕
株式会社ヒルストン代表取締役
1968年石川県金沢市生まれ。東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルート入社。20年以上にわたり新卒・中途採用支援に携わる。東京・富山・熊本・大阪での勤務を経て独立。
ヒルストングループとして税理士事務所への顧問先紹介、地域特化・職種特化型の人材紹介、中小企業に特化したM&A仲介及びアドバイザリー業務の3つを柱に事業展開している。
——年収が下がる可能性がある時、マネープランの側面でいうと特にどんなポイントを考えるべきですか?
ファイナンシャルプランナー 横田健一(以下、横田):お子さんがいらっしゃる家庭であれば、40~50代は子どもが高校生や大学生になり、まとまった教育費がかかるタイミング、という方も多いかもしれません。マイホームを買う場合は頭金を準備するために「2~3年、お金を貯めよう」と少し先延ばしするという判断もできますが、教育費の場合は「お金がないから、大学進学を1年待ってくれ」というわけにはなかなかいかないですよね。
ある程度蓄えがあれば、仮に転職に失敗して年収が下がるようなことがあってもリカバリーできます。逆に、カツカツな状態でのチャレンジングな転職は当然リスクがあります。
独身やDINKSの方であっても考え方は共通で、ある程度のお金が必要になるタイミングを予期しながら、転職のタイミングを考えていくのがよいと思います。年収の下限を見極めるという意味では、ファイナンシャルプランナーをはじめとしたお金の専門家に相談するのもいいかと思います。
――「守り」のプランニングをプロと固めておくと、判断しやすそうですね。40~50代の求人数自体は減少しがちとのことですが、中でも特にニーズが増えている、年収が上がっている領域はあるのでしょうか?
石坂:特に求人が増えている領域としては、新規事業の立ち上げメンバーや事業企画、経営企画といった専門職種へのニーズが増えている印象です。
また、これまでのスキルを生かして“斜めの転職”に成功するケースもあります。例えばこれまでずっと経理として歩んできた方であれば、他企業の経理として転職するパターンも当然あれば、専門性を生かしてコンサルティング企業へ転職することも。
経営戦略が複雑化している現代は、「専門性を生かして別の職種へ」はさらに増えていくのではと感じています。

石坂:会社によっては50歳、55歳といったタイミングで年収がガクッと落ちることもありますよね。おおよそ40代後半から、今後の社内での自分のキャリアの上限が見えてくることが多いようです。慣れ親しんだ会社に残って仕事を続ける道、60~70代まで働くことを考えて新しいチャレンジをする道、どちらも考えるタイミングではないでしょうか。
我々の会社では、東京の企業に勤めていた方を地方企業の経営幹部として転職支援することも多いのですが、お子さんの教育にめどのついたタイミングで新しく挑戦するケースは実は多いです。30代の頃は子ども優先で仕事や生活のサイクルをつくっていたご家族も、お子さんが独り立ちするとその限りではなく、自分の「この先」のライフプランを柔軟に考えられるようになるようです。
——東京から地方の会社に転職するのは、どんなバックグラウンドの方が多いのでしょうか。
石坂:都心に構える大手企業と比べると、地方の中小企業はどうしても人材不足になりがちです。既存社員の中から経営幹部に登用することに限界があったり、今後成長させたい事業領域に大企業出身者の経験が生かせそうという期待があったり。
逆に言うと、大企業は組織が大きいからこそ競争は熾烈。非常に優秀なのに、キャリアやポジションに行き詰まっている方が、違う環境で能力を十二分に発揮するケースも何度も見ています。
横田:私も40~50代のクライアント様に、転職を迷っているとご相談いただくこともあります。「役職定年」といわれても「55歳になったからといって何かができなくなるわけではないし、急に年収を下げられても……」と戸惑う方もいますよね。
転職以外の道としては、まずはできる範囲で副業をしてみて新しい仕事の可能性を探るのも今の時代はありかもしれません。収入源自体を増やせるメリットに加え、新たなネットワーキング、ひいては次の仕事につながることもあります。
あとは石坂さんもお話しされていましたが、子育てが一段落すると「家族を守るために稼ぐ」という意識から、「自分のやりがい、生きがいのために仕事をする」に、考え方がシフトするケースは私の経験でも多いです。生活リズムの変化は、仕事観の分岐点にもなりますよね。

横田 健一
ファイナンシャルプランナー
株式会社ウェルスペント 代表取締役
野村證券株式会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年に独立。FPとして家計相談やライフプランシミュレーションの実績多数。
「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。2023年6月、初の著書『新しいNISA かんたん最強のお金づくり』(河出書房新社)を発売。「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」監修。
石坂:何歳まで働くかも重要ですね。仮に70歳まで働くとすると、いま50歳だとしても、あと20年もあるんですよ! まあまあ長いですよね(笑)。
そうなると、お金のことを考えるのももちろん大切ですが、結局はあなたが楽しく働き続けられるかどうか。健康寿命がさらに延びていくであろうこれからの時代は、もっと大切になっていくと思います。
横田:公的な制度の側面で言うと、60歳を過ぎると年金を繰り上げで受け取れるようになりますし、高年齢雇用継続給付(※)などの制度もあります。60歳以降も長く仕事を続ける場合は、そういった制度も考慮に入れながら働き方を考えましょう、とアドバイスしています。
(※60歳以上65歳未満の従業員を対象とした雇用保険の給付金。60歳以降の収入が、60歳時点の75%未満にダウンしてしまう場合に補填として支給される)

石坂:これは、ケースバイケースだと思います。例えば、未経験の業界にポテンシャル採用で入ることは40代以降難しいのは事実です。培ったキャリアや経験などのバックグラウンドを生かせる場を見定める……という意味での“落ち着き”は必要になるかなと。
とはいえ、では挑戦がしにくくなるのか? というと一概にそうとも言えないと思います。なぜなら、培ったキャリアという基盤があるからこそできる大きなチャレンジもあるからです。
私自身、45歳で独立してから今年で11年ほど経つのですが、「(独立が)遅かったな、もっと早くしてもよかったな」と思うこともあったものの、今はこの先10年で何をしようか? と日々ワクワクしながら生き生きと働けています。
弊社では現在、人材紹介とM&A仲介(事業承継したい企業と、新たにオーナーになる企業や個人をマッチングする)という2つの事業を手がけているのですが、後者は創業当初は経験のない事業だったんですね。サラリーマン時代の知見をもとに、まず人材紹介の事業基盤を築いたことがその後の事業拡大につながっていきました。
私の場合は転職ではありませんが、過去20年のキャリアの積み重ねがあったからこそできる決断ではあったと思います。当然ですが、スキルと経験がしっかりある人は、年齢を重ねてもマッチする転職先は見つけやすいですね。

——マネープランの面ではいかがでしょうか? 歳を重ねると、転職時にチェックすべきポイントは変わってきますか?
横田:60歳以降の資金計画を考えるという意味では、退職金や企業年金があるのか、退職給付制度の有無は把握しておくと安心できるのではないでしょうか。
60歳以上の方に定年後も働いている理由を聞いた調査を見ると、60代前半は多くの人が「家計のために働いている」と答えているところ、60代後半になると「生きがいをもつため」が逆転するんです(2018年「50代・60代の働き方に関する調査報告書」、ダイヤ高齢社会研究財団)。
年収にかかわらず、やりがいのために70歳や75歳まで働く人もいれば、早めに仕事をセーブして悠々自適な生活を送る――という考え方もあると思います。それは各自の価値観次第ですし、選択肢をしっかり比べながら検討してもらえればと思いますね。

石坂:40代後半、50代以降で親御さんの介護を理由にUターン転職を検討する方は一定数います。私が過去にサポートした中だと、大手の商社でキャリアを積んだ60代の方が、90代の母親の介護をするために地方企業へ転職を希望されていたケースがありました。特定の地域の中で職を見つけるのは比較的難易度が高いのですが、それまでの経験と照らし合わせながらうまく実現する方はいます。フルタイムで働いたり残業したりが難しいと、「柔軟な働き方ができる会社」という条件で転職先を探す方もいます。
介護との両立は、単純に「仕事を辞める、変える」だけではなくバランスで考える必要がありますね。ご家族がいれば、パートナーとどう役割を分担するかも考えなくてはいけません。介護を理由に転職を検討している相談者には、そういった話を広くお聞きしたうえで、求人を探すお手伝いをしています。
横田:子育てと異なり、介護は突然発生することも多く、事前の準備や心構えがしにくい領域です。「どうしたらいいんだろう」と焦る方もきっと多いですよね。
お金の面で言うと、自分が支えなきゃ、時間もお金も捧げなきゃ、と思い詰めすぎないことがまず大切だと思います。「親の介護は、親が持っているお金の範囲で」が基本的な考え方だと考えてほしいです。そのために、公的介護保険などさまざまな国の制度や施策がありますから。
困った時は市区町村の窓口や地域の包括支援センターに相談すると、要介護認定を受ける手続きやデイサービスの紹介など生活面のサポートをしてくれます。介護保険は所得が一定以下であれば原則1割負担なので、仮に要介護5の認定を受けた場合、月の介護費用として約36万円かかった場合の自己負担は3.6万円ほどになります。
「たくさんお金がかかったらどうしよう」と身構える前に、ある程度知識を入れておくと、公的な支援がカバーしてくれる範囲が意外に広いこともわかりますし、不安も減るのではないでしょうか。

横田:わかる! という方も多そうな相談ですね(笑)。早めというのが45歳や50歳、60歳と、どれぐらいの年齢を指すかにもよりますが、自分が受け取れる公的年金や退職金などの金額を把握し、それと合わせて収入をどう確保していくかを考えましょう。年金などでいくら手に入るかを知らないまま会社を辞めてしまうのは、リスクが高いです。
退職後に貯金を使って生活する場合、例えばインフレによって計画よりも支出が増える可能性は十分にあります。それに備えて、資産運用も組み合わせていくことも大切です。会社を辞めてから年金を受け取れるようになるまでの無収入の期間がどれぐらいあるのか、生活費を調整する余地はあるかなど、不測の事態も含め、具体的なお金の流れを考えていくことが大切だと思います。
また、FIREもそうですが、仕事を辞めてから最初の半年~1年ほどは自由に過ごしたとして、だんだん飽きてくる、「仕事をしていたほうが楽しいかも」と思うようなケースも正直かなりあるんです。お金の話の前に、仕事を辞めたあとの時間の使い方、ライフプランそのものについて考えておくことも大事ですね。

――今まで仕事をしていた分がそっくりそのまま空白になると……かなりの時間ですよね。
横田:実際にデータで見てみましょうか。新卒入社から定年退職(60歳)までの労働時間は、フルタイムで働いた場合、年間でおよそ2000時間。それが40年続くと、8万時間になります。
では、定年後にどれぐらいの時間があるかというと、朝から晩まで1日あたり10時間を自由に過ごせると仮定して、20年で7万3000時間、30年だと10万9000時間になります。フルタイムで働いている40年の総労働時間よりも長いですよね。
――本当ですね! マネープラン以前に、仕事や趣味の領域で長く続けられる活動を見つけておくことも大事かもしれないですね。
横田:おっしゃる通りです。リタイアメントプランニングでは、「きょういく」と「きょうよう」が大切だと言われます。教育、教養ではなく、「今日行くところ」と「今日の用事」です。
例えば、毎週決まった曜日にスポーツジムへ行ったり、知り合いとランチに出かける用事をつくったり。予定を入れて行動をしないと、家にいるだけでは刺激が失われ、認知症のリスクなどが高まってしまうんです。毎日忙しく働いている中で「早く仕事を辞めたい」と考える気持ちはとてもよくわかるのですが、ではどんな人生を、どんな時間を過ごしたいのか、具体的に考えておくことをおすすめします。
石坂:M&A仲介の事業を手がける中で、「定年後にしっかり取り組むための事業を買いたい」という個人の方もいます。「仕事を続ける」選択肢には、企業に所属して働く以外にも、独立や、副業を充実させるという手もあります。さまざまな選択肢があると思いますね。
——仕事を続けるか、やめるかのシンプルな二択ではなく、転職について考えることが、ひいてはその後の人生を考えることにもつながるのだなと思いました。
石坂:普段は相談者の方からお話を聞いて転職についてアドバイスしていますが、今日のお話を聞いて、転職は個々人それぞれの人生のフェーズ、今後の人生計画と密接に結びついていると改めて認識しました。そういった視点も交えて総合的にお話しすると、より本質的なアドバイスができそうです。
横田:キャリアや仕事の話とどう生活していくかという話は、切っても切れないですよね。相談者の人生をキャリアの面から見ているのが転職アドバイザー、家計やお金の面から見ているのがファイナンシャルプランナーなのかなと思いました。両者の観点を踏まえて一体的に価値を提供できるサービスが世の中に広がっていくと、多くの方の悩みにより明確に寄り添えるのかなと私自身も感じました。
(構成:加藤智朗、編集:山崎春奈、撮影:工藤朋子)