特集
特集
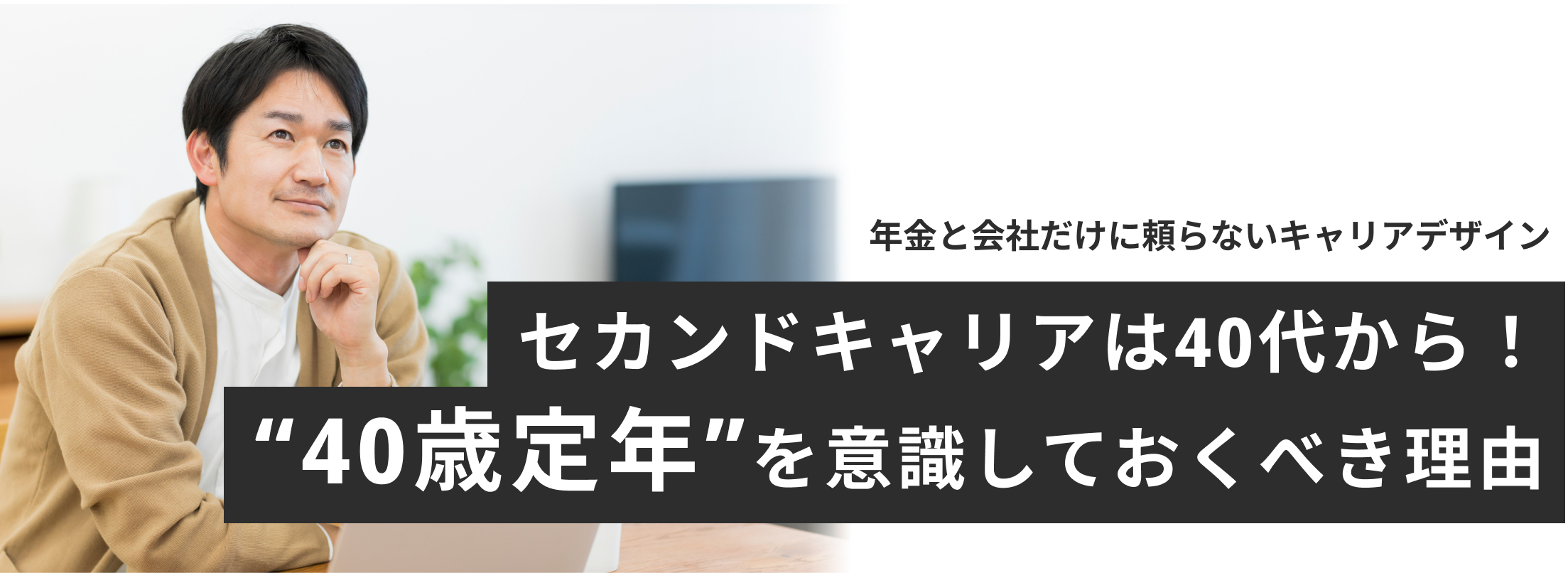
最近、浮上してきている「40歳定年制」という言葉を皆さんは耳にしたことがあるだろうか? 「40歳定年」とは言っても、実際に40歳が定年になるというわけではない。個人で40歳を節目として意識し、キャリア形成をしようという考え方である。
Contents
「40歳定年制」とは、内閣官房国家戦略室のプロジェクトチーム「国家戦略会議フロンティア分科会」が提案した雇用政策案。企業内の人材の新陳代謝を促進し、雇用の流動性を高めることを目的としている。
具体的には、企業が従業員の定年年齢を最短で40歳まで引き下げることを認めるもので、これにより企業内の人材が固定化するリスクを減らし、競争力を維持する狙いがある。また、早期定年を選ぶ企業には、退職者への再教育や所得補償の義務を課すことも提案されている。
この制度は、単に40歳で退職させるというものではなく、雇用契約を有期とすることで労働市場の流動性を高めることを目指している。
出典:40歳定年制とは――提言の背景、そのメリットとデメリットは – 『日本の人事部』
急速に高齢化が進む日本では、現在企業などで働く勤労者の定年制度を60歳から65歳へ延長し、これをさらに70歳、あるいは75歳へと延長していく流れがある。 そこで、75歳まで息切れを起こさず働くために、40歳という年齢を節目に、これまでの経験を活かして、セカンドキャリアを築くという視点が生まれるのだ。
現在、日本の労働環境は戦後最大の過渡期を迎えているといっていい状況にある。それに伴い新しい概念や価値観が出現するのは当然の流れであろう。 これまでの価値観はきれいさっぱりリセットし、新たなモノサシでキャリアをデザインすべき時だ。というわけで、今回は、キャリアデザインの大前提となる労働観の変遷についてまとめておきたい。
2013年春から、企業には65歳まで就労を希望する従業員の雇用が義務付けられた。実質的な定年の延長である。 年金財政悪化にともなう年金支給開始年齢の65歳への引き上げを受けた処置であり、実質的な年金カットと言っていい。
年金財政ひっ迫が継続していることを考えるなら、50歳以下の世代はさらなる年金カットに備えるべきだろう。 それが「支給開始年齢のさらなる引き上げ」か「年金自体のカット」かはわからないが、いずれにせよ我々は70代まで現役で働き続ける覚悟をしておくべきだ。
ただ、そうなると、大きな問題が残る。(自立した生活が送れるとされる)健康寿命は日本人男性で71歳とされているが、 仮に70歳を過ぎても今の会社に面倒を見てもらうとするなら、人生のほぼすべてを会社に丸投げすることになってしまう。果たして、それは個人の人生として幸福なのだろうか。
実は、もともと定年制度は終身雇用制度に区切りをつけるために生み出されたものであり、かつては55歳が一般的だった。 その年齢なら、組織に下駄を預ける働き方もないではない。本当にやりたいことや培ったスキルを使った第二の人生は、定年後にまだまだ十分取り組める時間が残っていたからだ。
だが、65歳ではそのための時間はほとんど残されない。70歳ならほぼゼロ、事実上、働き方=生き方となってしまう。 つまり、会社にキャリア決定権を委任し、与えられる仕事を何でもこなす生き方は、人生そのものを他人の手にゆだねてしまうということだ。
なんだか昔の社会主義国みたいな話であり、21世紀のあるべきキャリアデザインとはとても筆者には思えない。
理想を言えば、10代後半の時点で自身の大まかなキャリアデザインを描き、そのために必要なスキルを身につけるために大学等の高等教育機関に進むべきだろう。 義務教育課程からキャリア教育をスタートさせ、偏差値やブランドではなく「何が学べるか」で進学先を選ぶべきだろう。
だが、残念ながら現在の日本はそういう環境ではない。 多くの人は社会に出てからOJTによってさまざまなキャリアを身につけていくというスタイルで人材育成されることになる。
だからこそ、40歳前後というのは重要な節目だと筆者は考えている。その年になれば、それまで積み重ねてきたさまざまなキャリアの中から自身で気に入ったパーツを組み上げ、 望むようなキャリアがデザインできる事だろう。
関連情報:40代で転職する際におすすめの資格|取得するメリットや選び方も紹介
そこで“40歳定年”の考え方に基づいて、第二の就活をしてもいいし、 転職しなくても社内公募などを通じて自身のキャリアデザインに沿った職に就く努力をするだけでもいい。そうした努力は、目の前の仕事により深くコミットできるようになることを通じて、 各人の人生をより充実させてくれるだろう。
もちろん、これまで通りとにかく会社にしがみつくという選択肢もないではない。だが、一般的に雇用期間が長くなればなるほど、 全国転勤や長時間残業といった甘受せねばならない不利益は増えるものだ。さらなる滅私奉公を要求されるくらいなら、 人手不足を機に活性化している中途採用市場に目を向けるのが合理的だろうというのが筆者の意見だ。
成功例:専門性を活かして年収アップと働き方の改善を実現したTさん
Tさんは、40代の男性で、建設工事会社の設計部でマルチに活躍していました。しかし、自分の設計スキルが他の企業で通用するか不安を感じていました。そんな中、株式会社ファイブスターコンサルタントのサポートを受け、設計会社への転職を決意しました。
コンサルタントのアドバイスにより、Tさんは施工性への配慮や積算の精度が設計会社で重宝されることを理解し、転職を果たしました。結果として、設計会社では建設全般の知識が高く評価され、年収アップとワークライフバランスの改善を実現しました。
また、流通業界の中規模クラス企業でキャリアを重ねてきた方が、新たに流通事業を立ち上げる大手商社に事業責任者として迎えられた事例もあります。これらの成功事例から、40代の転職には専門性を理解できるコンサルタントの活用が重要であることがわかります。
出典:【40代転職】40代の転職で「コンサルタント(転職エージェント)」を活用して成功させる方法
Wさんは、40歳の男性で、大学卒業後に広告会社の法人営業担当として4年間勤務した後、化学品商社で機能化学品の営業に約12年間携わっていました。しかし、知人が立ち上げる新しい会社に誘われて退職したものの、直前になって入社できない状況に陥り、再就職活動を開始しました。
株式会社ゆーらむのコンサルタントである遠藤こづえさんは、Wさんの職務経歴書に目を留め、スカウトしました。40歳という年齢と1年以上のブランクがあることで苦戦していたWさんですが、遠藤さんはWさんの化成品営業の経験と人柄に注目しました。
最初の面談では、Wさんは自信を失っており、覇気が感じられませんでした。しかし、遠藤さんはWさんの素敵な笑顔に気づき、「その笑顔を面接で見せましょう」と励ましました。さらに、自己紹介文の作成を依頼し、Wさんが自分の言葉で自分をアピールできるようにサポートしました。
結果として、Wさんは化学工業薬品・合成樹脂・ガラス繊維・石油製品を扱う総合商社T社に内定を獲得しました。T社は「人柄重視」というキーワードを重視しており、Wさんの誠実な人柄が評価されました。
現在、WさんはT社で営業職として活躍し、再び自信を取り戻しています。
出典:退職から1年以上が経過した40歳。苦戦していた状況を好転させたコンサルタントのサポートとは?
転職という選択肢に対して、「具体的に何から手を付けてよいのか分からない」という人もいるかもしれない。そういう人は取りあえず実際に転職サービスを活用して転職活動を進めてみることをおすすめしたい。転職コンサルタントによるキャリアの棚卸しや採用担当との面接を通じて、自分に足りないものがきっと見えてくるはずだ。
関連情報:コンサルタントを探す
関連情報:コンサルタントとは
今回のポイント

年金財政はひっ迫しており、現在50歳以下の世代は少なくとも70歳までは現役で働くことを意識してキャリアデザインしておくべきだ。

「会社にキャリア決定権を預ける代わりに定年まで面倒を見てもらう」というやり方は55歳定年時代のもの。65歳を超えて働かねばならない時代にはデメリットの方が目立ってしまう。

これからの時代、自身でキャリアデザインし仕事に前向きにコミットできるようにすることは、人生をより充実したものに変えていくことでもある。

城 繁幸(じょう しげゆき)
人事コンサルティング「Joe’s Labo」代表取締役。1973年生まれ。東京大学法学部卒業後、富士通入社。2004年独立。
人事制度、採用等の各種雇用問題において、「若者の視点」を取り入れたユニークな意見を各種メディアで発信中。代表作『若者はなぜ3年で辞めるのか?』、『3年で辞めた若者はどこへ行ったのか-アウトサイダーの時代』、『7割は課長にさえなれません 終身雇用の幻想』、終身雇用プロ野球チームを描いた小説『それゆけ!連合ユニオンズ』等。